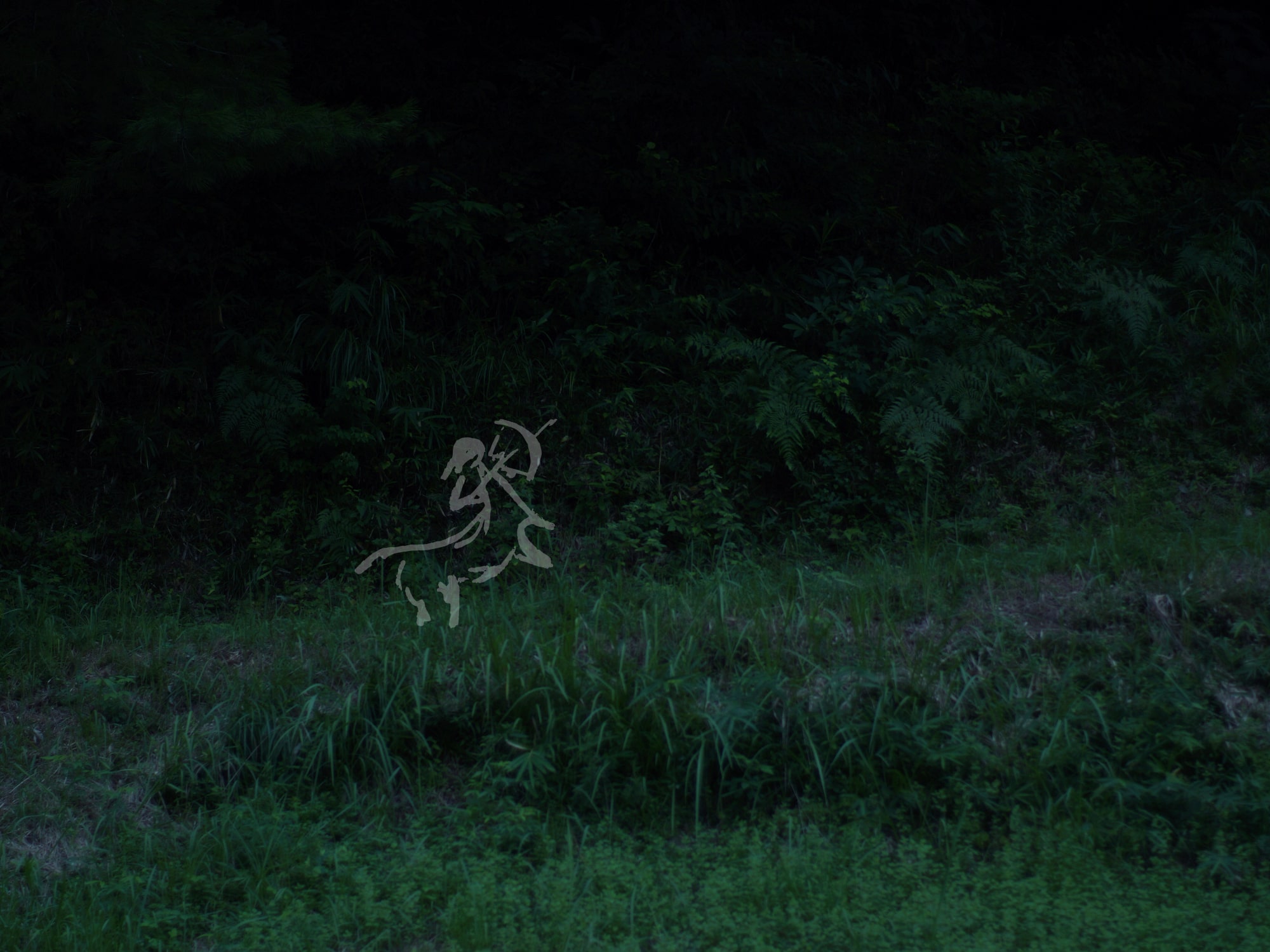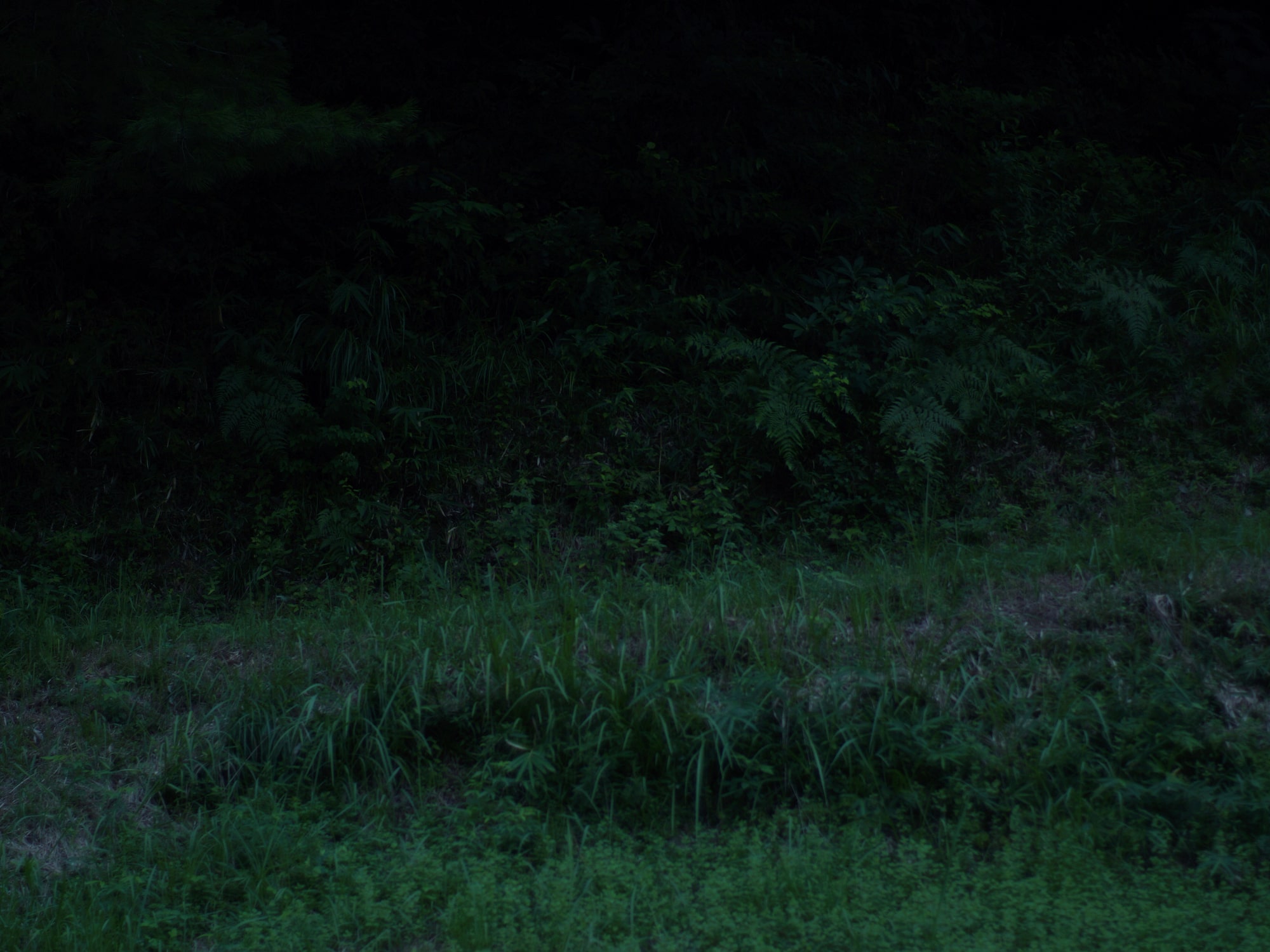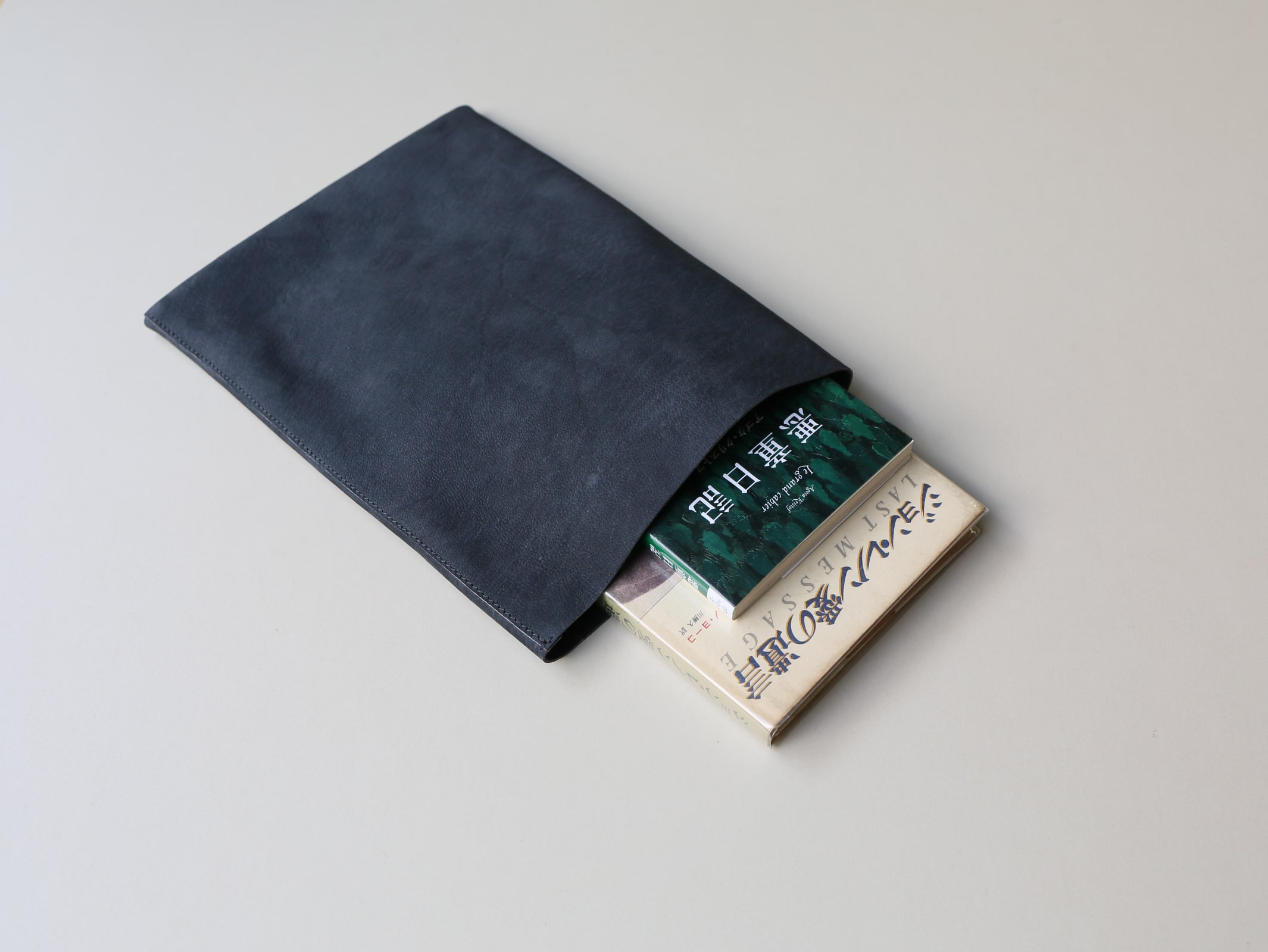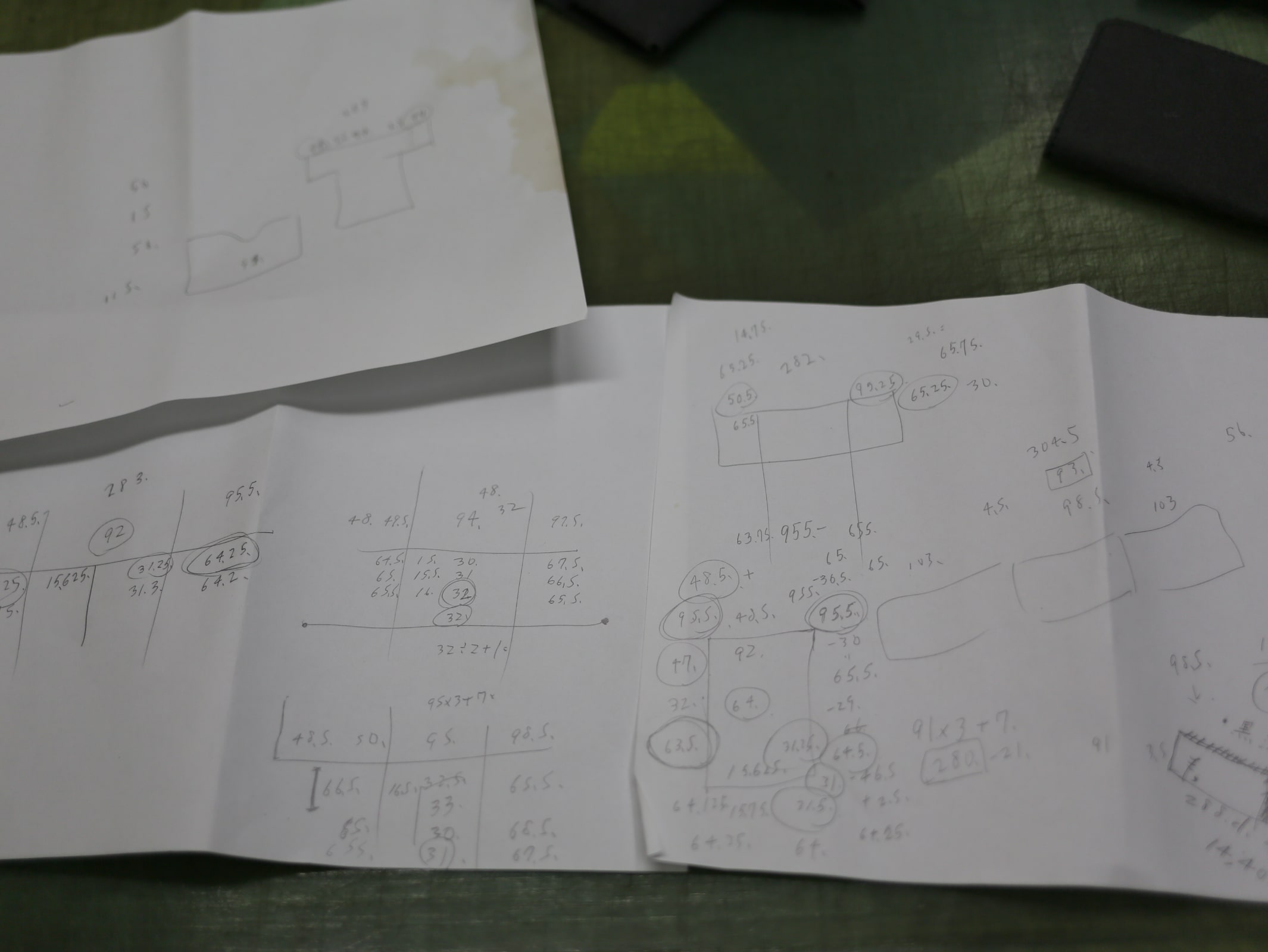あたらしく、key strapとlink strapというアイテムを作りました。
裁断して残った小さな革を使って制作する、Over the rainCowのアイテムとして、スウェードの革で作りました。
Over the rainCowのアイテムを作るのは、簡単なようでいて、難しいです。
ただ端革を使いましたというものにならずに、小さい革ならではのリアリティを持ったものにしたいと自分でハードルを上げている感があります。小さな革の傾向と、アイテムの選定とデザインが、いいポイントで交わり活きるようにイメージしながら考えました。
key holderは指にちょこんと引っ掛けて、
key strapは手首に通して持つことができます。
link strapは、カバンの持ち手と物をつなげるアイテムです。
ー
【key strap】
手首に通して使える、スウェードのキーストラップです。
手に通した時に心地良いように、柔らかな革で制作しました。
鍵を振った時に、キャッチしやすいサイズ感です。
制作当初は、手首に通さず手で持つことを想定して制作していましたが、鍵を持っていて、手を使いたいシュチュエーションが多々あり、手首に通せるようにしました。
ー
key strap
size : w12mm
length : 185 mm (キーリング含む)
key strapはこちらからご覧下さい。
【link strap】
link strapは、カバンの持ち手と物をつなげるストラップです。
カバンの中から、ストラップをひょいと引っ張って、つながっているものを取り出します。
鍵をつけたままで、扉の開け閉めが出来る長さで制作しました。金具はカラビナを使用していますので、金具からの取り外しも簡単にできます。
かばんの中で迷子になりがちな物とつなげてお使いください。
僕はこのlink strapに、小さな懐中電灯をつけて使っています。
住んでいる地域は11月頃までまむしが出ます。
街灯がないので、まむしを踏んで噛まれた話もたまに聞きます。
その話を聞いてから、夜道を歩くときは、懐中電灯で照らしていましたが、
懐中電灯が手元にないこともあり、踏んじゃうかな〜、とビクビクしながら歩いてました。
小さな懐中電灯が手元にあると、結構な安心感があります。
ー制作話ー
ロスがないような革の作り方をしたり、端革を使い切るアイテムを作ったり、傷を生かすアイテムも作っているけど、素材が作り続けられることを前提にした、大切さだったように思う。
なくなっていく素材との別れをとおして、素材というものが、あんがい儚い存在であると感じた。
ロスがないように工夫しているはずの革作りも、実際には余っていて、全部使えてはいない。(革の作り方も、変えることにしましたが、それはアイテムを作ったときにお話しますね。)
素材を大切に扱わないと、素材はどんどん無くなっていく、みたいな意識もある。
なくなっていく素材との別れをとおして、素材というものが、あんがい儚い存在であると感じた。
ロスがないように工夫しているはずの革作りも、実際には余っていて、全部使えてはいない。(革の作り方も、変えることにしましたが、それはアイテムを作ったときにお話しますね。)
素材を大切に扱わないと、素材はどんどん無くなっていく、みたいな意識もある。
実際には、僕がロスを出すことと、素材がなくなることの因果関係はないのだけど、そのサイクルはどこかで繋がっていると思ってしまう。
この小さなアイテムが、お役に立ちますように。